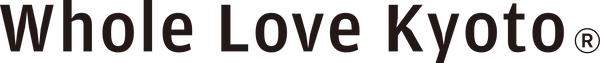夏次郎商店とこぎん刺し | 01
Share
青森の民芸、その代表格「こぎんし刺し」を知っていますか。
僕はそんなに知りませんでした。
最近の「こぎん刺し」は、洒落ててかわいい。
その“最近”の流れをつくった第一人者・夏次郎商店さんと
WLK の HANAO SHOES がコラボする
ということで、せっかくの機会なので青森まで行ってきました。
夏次郎のこぎん刺し鼻緒を HANAO SHOES にすげる企画。
会場は、弘前市(ひろさきし)のギャラリー CASAICO。
寒かったけど、行った甲斐がありました。
こぎん刺し作家・夏次郎さん(写真NG)と
お話した記録をここに公開します。
弘前のこと、こぎん刺しのこと、青森の伝統産業のこと など。
夏次郎商店とこぎん刺し | 01
「こぎん刺し」を家庭の時間に習う、青森
基礎知識「こぎん刺し」のルーツ。
「こんなのこぎん刺しじゃない」と言われた時代。
夏次郎商店とこぎん刺し | 02
結局、刺繍なんて、誰でもできる。
専門職が分業で作るから、付加価値がつけられる。
鼻緒・夏次郎の理由。
夏次郎商店とこぎん刺し | 03
知らなかった、HAMAO SHOES。
夏次郎さんとのお話会を終えて
「こぎん刺し」を家庭の時間に習う、青森
酒井:
青森では「こぎん刺し」を家庭の時間に習うんですよね。
夏次郎さん:
そうです、私は高校生の時の家庭科の授業で習いました。 皆一度は工芸に触れる授業の一環として、学校で習っています。
酒井:
中学ではなくて高校?
夏次郎さん:
高校ですね。
酒井:
男の子とか苦手そうですけど、どうですか。
夏次郎さん:
いえ、そこまでは。1日で覚えれますし、ワンポイントなんてすぐなので。
刺したらそれを業者さんがコースターなどに仕立てます。興味なくても一瞬です。
酒井:
(他の青森の伝統産業である)「津軽塗」を習ったりもするんですか?
夏次郎さん:
「津軽塗」の講習はないです。
ただ、誰の家にも必ず津軽塗のお椀か、お盆か、お箸があります。
酒井:
僕もお箸を持ってます。
夏次郎さん:
津軽塗ですか。
私、生まれて津軽塗以外使ったことないです。

酒井:
かっこいい。
夏次郎さん:
柄が特徴的なマーブルというか、割と好き嫌いが分かれる塗りなんですけど。
酒井:
青森の地場産業は、津軽塗とこぎん刺しと……
夏次郎さん:
あと何だろう、ヒバとか。
酒井:
そうか、ヒバ。
夏次郎さん:
黒石に行くと、こけしも作ってますし。
酒井:
こけし。 その中でも高校で習うのは「こぎん刺し」。 お手軽だからですかね。
夏次郎さん:
そうだと思いますよ。
酒井:
夏次郎さんは高校で1回しかやってない。
1回しかやってないのに、それが今仕事になっているわけです。
夏次郎さん:
そうですね、はい。楽しかったんでしょうね。
酒井:
1日だけなのに、覚えてるんだ。
夏次郎さん:
その授業のすぐ後に、もう1回始めたんです。
友達にプレゼントするために「こぎん刺し」の印鑑ケースみたいなものを作りました。
酒井:
僕もそれ欲しいな。
夏次郎さん:
あるのかな、加工場。
昔は街に、布さえあれば小物を作ってくれる加工場がたくさんありました。
青森市の方は廃れてしまってもうないですけど、
弘前は工芸をとっても大切にするので、まだあるかもしれません。
酒井:
その“工芸を大切にしている” の具体的エピソードを教えてください。
夏次郎さん:
今となっては(こぎん刺し)皆さん気軽に作れますけど、
10-20年前は昔から伝わる“紺に染めた麻地に、生成りの糸”が本当ベーシックで、それしか「こぎん」じゃないっていう感覚でした。
でも今どんどん変わってきてて、弘前のお店とかでも、赤とか青とかの「こぎん刺し」の小物を展示販売してたり、
ストールとかシャツとかにラインで刺したり。
そういう新しい「こぎん」が弘前はすごく盛んで、おしゃれなこぎん刺しいっぱいあります。
酒井:
伝統を守るというより発展させたり、あそんだりして、大切にしているってことですね。
基礎知識「こぎん刺し」のルーツ。

酒井:
王道の、絹に生成りのこぎんはもうなくなりましたか。
夏次郎さん:
作り続けている職人さんはいます。
紺地の麻は「からむし」といって、とても貴重なものです。からむしを作る人あまりいないんですけど。
酒井:
からむし?
夏次郎さん:
「からむし」というのは、イラクサ科の植物の「芋麻」から糸を紡いで織った「からむし織」のことで、それを藍染したものがこぎん刺しに昔から使われていた布です。
昔、政策で農民は麻しか着れなかったんですよ。冬はさすがに寒すぎて死んでしまいますので、何も染めてない生成りの糸を麻の生地に刺すことで防寒にしていました。
そういう野良着とかを作っていたのが一番最初。今もその当時の色や質感、素材を大切にしている人たちもいます。
酒井:
こぎん刺して厚くするってことですね。
で、ただ刺すのもなんなので幾何学模様でお洒落にしたのが「こぎん刺し」のルーツ。
でも、今はわざわざそんなことしなくても、あったかい服たくさんある。
それを買う人って、どんな人なのかな。
夏次郎さん:
野良着としては使わないのは当然なので、
それがだんだん小さくなり、例えばテーブルに。
酒井:
なるほど。
夏次郎さん:
着るものからは脱却してしまって、コースターとかランチョンマットであったり。
一度規模は縮小したんですが、今はカラーがどんどん増えてきて、クッションカバーやベットカバー、ストール、帽子……。
アイテムが増えて、また着るものとしても広がりつつある感じですね。
やっぱりお手軽な手芸という域は、お教室なども流行っているせいもあって、まだ脱却しきれていない印象。
酒井:
なるほどね。
紺に生成り糸のベーシックな「こぎん刺し」。
夏次郎さん的には、それをずっとやっている人が「こぎん刺し」界では『本流』みたいな。
夏次郎さん:
本流だと思います。
酒井:
そうなりますよね。
今、いろんな色使ったり、教室で習ったりという様なムーブメント? 「こぎん刺し」のカルチャーが広まってるんですよね。
そんな中、『本流』の知り合いはいるんですか?
夏次郎さん:
いないです。私は高校で習ったきりなので。
大御所と呼ばれる先生が4、5人全国に散らばっていらっしゃるんですけど、誰かに師事するとかはしていません。
「こぎん刺し」に詳しい人が展示会に来られて「どこのお教室で誰に師事されて」とかよく聞かれるんですけど、
私、ほぼ独学でなので、伝統に沿ってるかと言われるとどうなんだろうなという。
酒井:
うんうん。でも大御所に師事したら、沿ってるってことになるのも、またちょっとね。
夏次郎さん:
箔じゃないかな、大先生についたとか。
でも習うことも大切なことだと思います。
酒井:
そうですね。先生が見てきた景色を弟子にも伝えているはずだし。
で、ちょっと話を戻しますが、結局、夏次郎さんは「こぎん刺し」を高校で習って、友達に作ってあげて、そこからずっとやってるってことですか?
夏次郎さん:
ちょっと間があいて。結婚を機に青森を出た時に、なんだろう。
酒井:
どこへ行ったんですか?
夏次郎さん:
最初は仙台。
でなんだろう…… 端的に言うと、地元のモノになんとなく触れていたいなという気持ちがあって、
前好きだったこぎん刺しをやってみようかなと。
やってるとだんだん楽しくなってきて、じゃあもっとこだわってみようとなって。
で、売れるんじゃないかというところまでいって。
「こんなのこぎん刺しじゃない」と言われた時代。

夏次郎さん:
はじめは売ってはなく、自分で使っていましたね。
どこで売ったらいいのか分からないし、
私が始めた頃は、本流の本津軽のこぎん刺しがまだまだ主流だったので
「こんなのこぎん刺しじゃない」
「こんな色じゃない」
「こういう小物類って……」
ていう時代だったんです。
今は全然違いますけど。
酒井:
それ何年ぐらい前の話なんですか?
夏次郎さん:
始めたのが2012年。
その頃はまだ閉鎖的だったので、青森に持ってくると「こんなのこぎん刺しじゃない」とか言われました。
もっと言うと、私は青森市出身で弘前じゃないから「あなたのちょっと違うわね」とか。
酒井:
ちょっと待って、質問。
「こぎん刺し」は弘前のものなんですか。
夏次郎さん:
弘前も、なんですけど、青森市は違うんですよ。
「こぎん刺し」は3箇所ぐらい発祥地があって、それぞれにちょっと作りが違います。
「みしまこぎん」ていって肩に3本線が入ってるやつとか、地域によって模様が違って、弘前もその1つなんです。
酒井:
全部青森県?
夏次郎さん:
青森県内です。
でも青森市は違う。
始めたばっかりの頃は「青森市の人が作ったなら、本当のこぎんじゃないよね」っていう時代だったんですね。
酒井:
なるほど。
夏次郎さん:
大変苦労しました。
なので、ちょっと青森から離れて、東京で年に1回あるクラフトイベントに出しはじめました。
何年かそこで雑貨ばかりやっていたんですけど、その頃に「こぎん刺し」が青森市とか弘前関係なく、
本流も何も関係なく、みんなが楽しめるお手軽工芸に変わったので。
酒井:
変わっていったんですね。
夏次郎さん:
変わって、作家が飽和状態になったので、私は鼻緒だけにしました。
酒井:
!今めちゃくちゃ早送りしましたね。
夏次郎さんがいろんな色で「こぎん刺し」やりだした時は、
夏次郎さん:
そういう人はいなかったですね。
酒井:
一応、革命ですよね。
夏次郎さん:
いやどうなんですか、
酒井:
小さな革命です。 青森から遠く離れたところで。

02 に続く
夏次郎商店 Instagram:
@kogin_natsujirou
ギャラリーCASAICO Instagram:
@casai